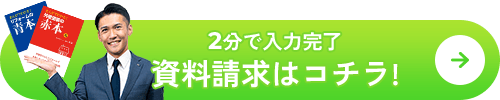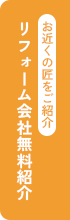nLDKは聞きなれないかもしれませんが、3LDK、2DK、1Kと聞くとイメージできると思います。
LDKはみなさんご存知、リビング(living)とダイニング(dining)、キッチン(kitchen)の頭文字を取った略語です。nは数学で習った自然数で、LDKの他に、寝室や子ども部屋、洋室や和室といった居室がいくつあるか?を表します。
「一人暮らしなら1DKで十分でしょ?」「子どもが増えたから、2LDKでは狭い。最低でも3LDKは必要だ。」といった会話は、当たり前になっていますが、このnLDKという建築用語はいつ頃から日本で使われているのでしょうか?
nLDKという概念は、1942年から始まり、80年以上続いていることに私は驚きました。
戦前の住宅の間取りは、座敷や茶の間、台所と土間といった部屋を襖や障子で仕切るだけでしたが、明治時代に西洋文化の影響で、洋室が増えてきました。また、父親が絶対的な権力を持っていた家庭の形から、個人を重視する生活空間を重視するようになりました。
第二次世界大戦中に日本各地の住宅が焼失し、短期間で大量の住宅供給が必要に。さらに、これまでの木造住宅よりも燃えにくい鉄筋コンクリート造(RC造)は高コストのため、限られたスペースを有効活用できる間取りが必要でした。
試行錯誤の中、「食事」と「寝る」をわける「食寝分離」の考えからダイニングキッチン、DKが生まれ、公営住宅に「51C型」、後の2DKの間取りが採用。高度経済成長期に、家族のくつろぎの場としてリビングも追加され、nLDKという形になりました。
nLDKという間取りは、画一的に作るマンションや建売住宅で重宝されますが、ライフスタイルが多様化する現代において、注文住宅で家を建てる場合や、リノベーションをするときはnLDKという概念に縛られない事例が増えています。今後、このnLDKという概念がどのように変化していくのか楽しみです。