
とにかく対応が早い!
- 工事内容
- 屋根・外壁塗装、階段シート工事
- 地 域
- 京都府 宇治市

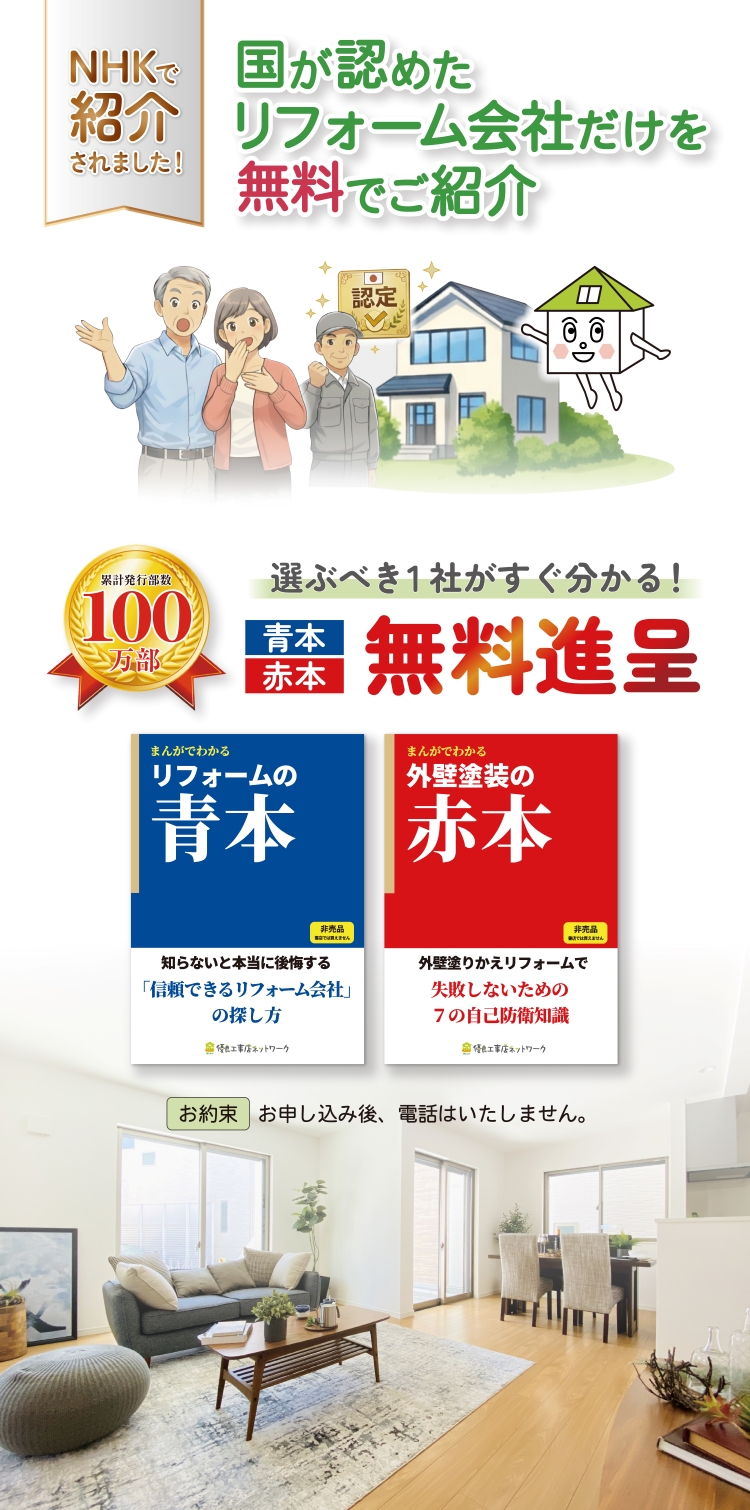
どこに頼めばいいの…?
基準
国が認めた「建設業許可」の会社を。
実は多い「無許可」の業者。
仕上がりも安心も大きく変わります。
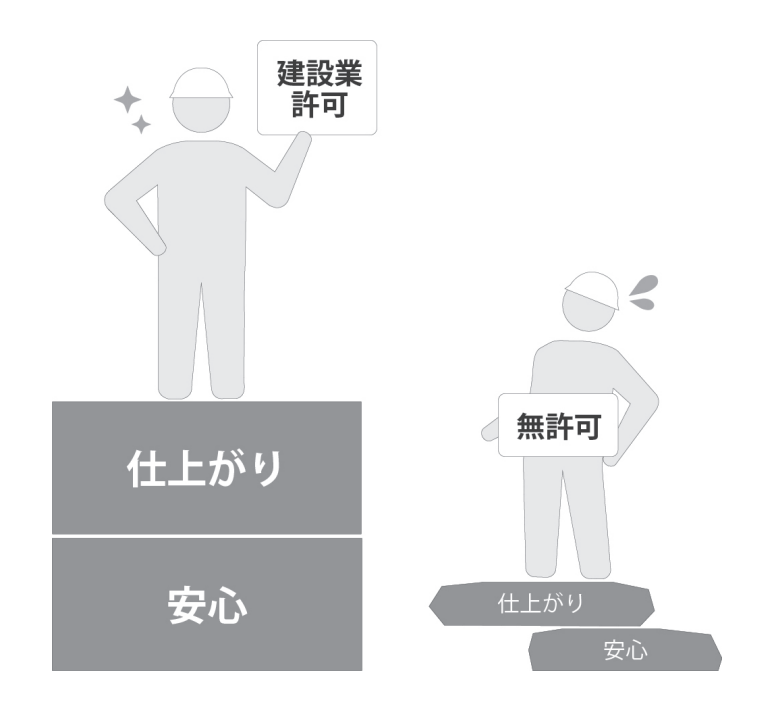
基準
自らしっかりと工事する会社を。
下請け任せの「丸投げ業者」は、
中間マージンで、割高になることも。
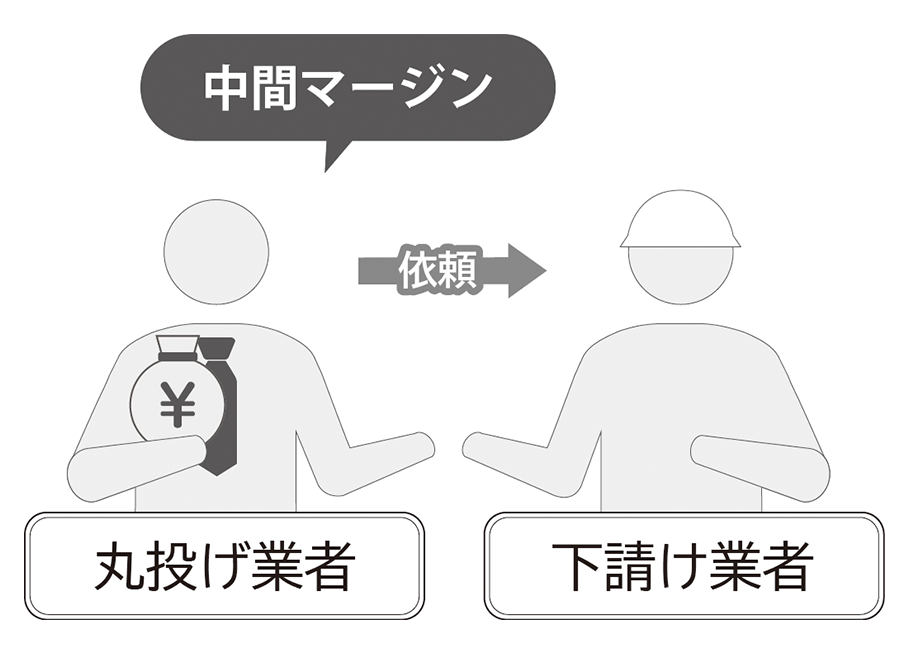
安心できる工事店だけをご紹介する仕組み。
・国の「許可」がある
・自社で丁寧に工事する
この条件を満たした会社だけ。
全国約48万社の中から、1,150社に厳選。


国内唯一!他では得られない
国内唯一!他では得られない
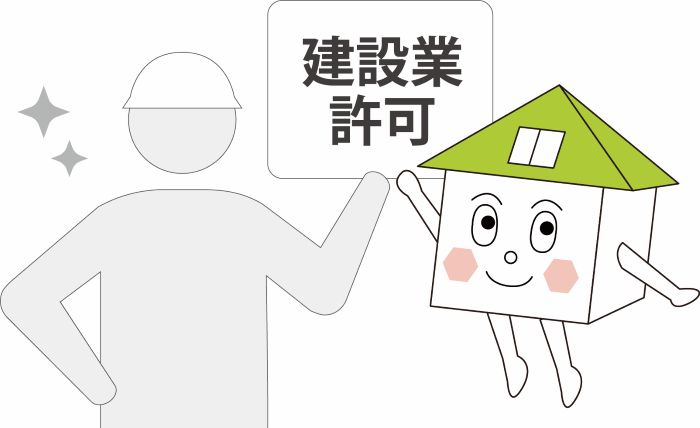
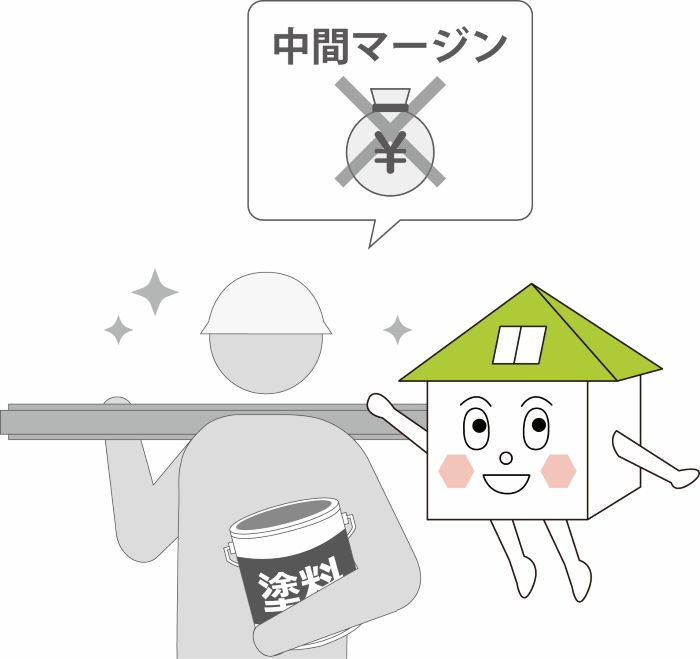
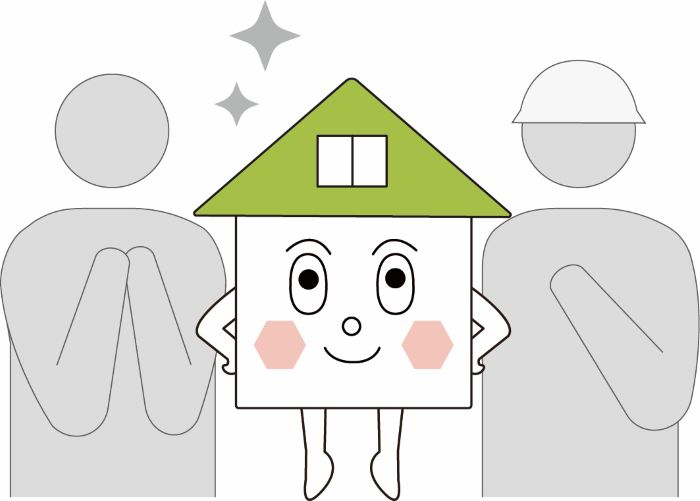
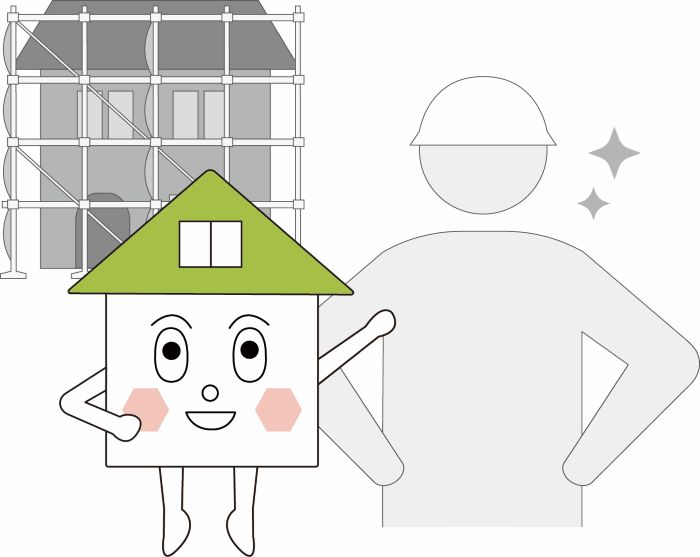
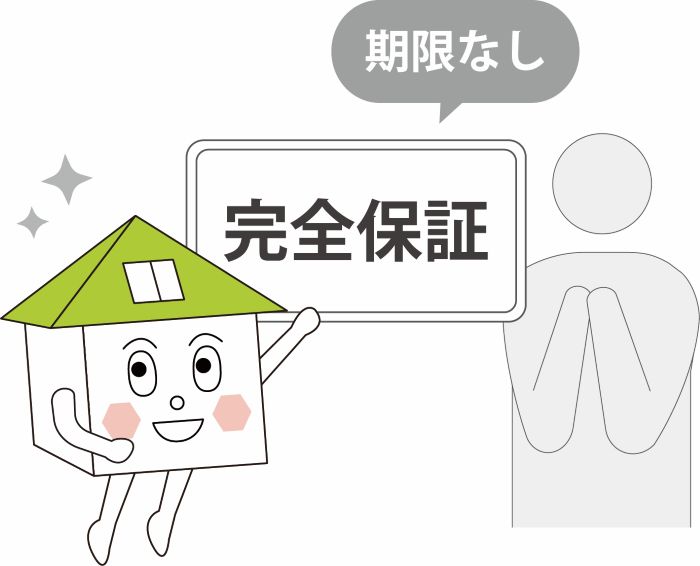
お約束
優良工事店ネットワーク 代表
堤 猛・安藤勉(建築士)
リフォームでは、不誠実な業者による「泣き寝入り」が後を絶ちません。私たちは、お客様にそんな思いをさせるくらいなら、会社をたたむ。この覚悟で20年以上、誠実に向き合ってきました。
紹介した会社が迷惑をかけたときは、当社が責任を持って全額を負担し、解決します。
「信じてくださったお客様を、決して裏切らない」その姿勢を、これからも貫きます。

はじめてでも、かんたんです。
むずかしい手続きはありません。
ご相談から工事後の保証まで、私たちがずっとサポートします。

どうぞお気軽に。電話・WEBどちらでもOK。
「相談だけ」でも大歓迎です。

選び抜いた優良工事店だけをご紹介。
現場を見て、無料でお見積もり。

内容と金額にご納得のうえでご契約。
完成まで責任をもって対応します。

不具合もすぐに対応。「期限のない保証」で、これからもずっとお守りします。
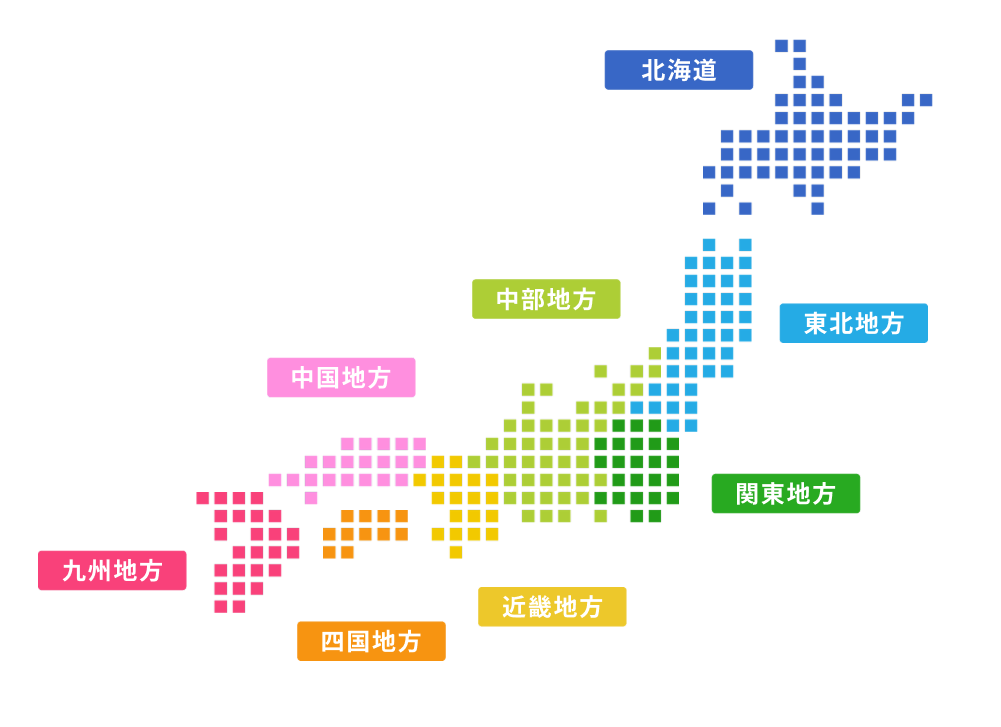


とにかく対応が早い!

安心してお任せすることができました。
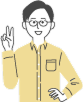
自分達自身が満足させて頂きました

リフォーム補助金・減税制度とは?金額や対象範囲、申請時期と注意点を解説
リフォーム補助金・減税制度とは?>





2025.12.17


2025.12.17