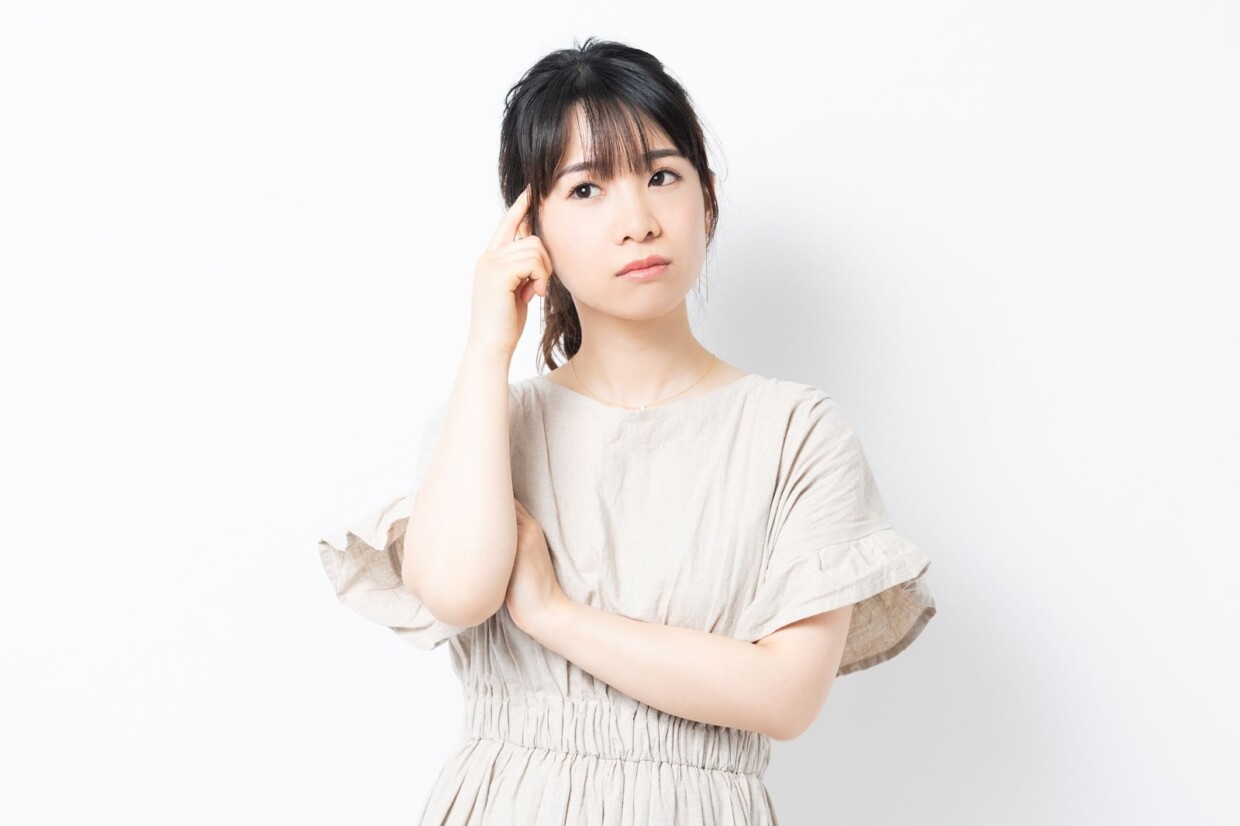
屋根リフォームは住まいを長持ちさせるために欠かせない工事ですが、残念ながら「詐欺」も横行しています。
「今すぐ修理しないと雨漏りする」「今日契約すれば安くなる」と不安をあおるケースは後を絶たず、不要な工事や高額請求をされる被害が各地で報告されており注意が必要です。
警察庁や国民生活センターなど詐欺に詳しい関係機関は、屋根修理をめぐる訪問販売トラブルは年々増加傾向にあり、特に高齢者世帯が狙われやすいと注意喚起を行っています。
そこで本記事では、屋根リフォーム詐欺の特徴や代表的な手口、被害に遭ったときの相談先、そして日頃からできる予防策について詳しく解説します。
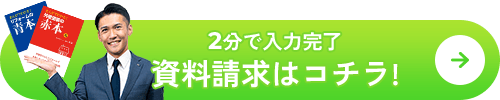
この記事の目次
屋根リフォームの詐欺は増加中!よくある手口とは

屋根リフォームをめぐるトラブルは増加しており、特に「点検商法」が多発しています。
様々な種類の詐欺や消費者被害の相談に対応している国民生活センターによると、手屋根リフォームで点検商法による相談件数は2022年は相談件数が8,166件でしたが、2024年では19,215件と大幅に増加しています。
屋根修理に関する相談件数は確実に増えており、日頃から詐欺に遭わないように注意が必要です。この章では警察庁発表の最新統計や、よくある手口を見ていきましょう。
参考:国民生活センター 訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
特定商取引関連の被害相談が過去最多警察庁の発表によると「点検商法」が過去最多
突然自宅を訪問して「無料で点検します」と近付き、実際には不要な工事を勧める手口は報道での注意喚起も盛んです。
警察庁の発表によると、2024年の統計では警察に寄せられた「特定商取引関連」の被害相談が、前年2023年と比べると約1.5倍の1万7703件に上り、過去最多になったことがわかりました。
国民生活センターの統計と同様に悪質なリフォームによる被害は多いと見られており、65歳以上の高齢者からの相談も最多の48.7%にも上っています。
被害の多さから報道機関も多く悪質リフォームへの注意喚起を行っており、2025年3月には日本経済新聞などの報道機関も大きく報道しています。
参考:警察庁 令和7年3月発表 令和6年における 生活経済事犯の検挙状況等について
参考:日本経済新聞 訪問販売の相談2倍に急増 24年、悪質リフォーム拡大
① 突然訪問し屋根の劣化を指摘する
「屋根が割れている」「今すぐ直さないと雨漏りする」と不安をあおり、強引に屋根リフォームの契約を取り付ける手口が後を絶ちません。特に台風などの自然災害後に訪問されると不安に陥り契約に至りがちです。
屋根材には耐用年数があるため、傷みの発生にはある程度の目安があります。ご自宅の屋根材の耐用年数を把握しておくことで、強引な契約を防ぐ効果があります。(※)
屋根材には種類ごとに寿命があります。突然の訪問で「劣化」と断定されたら、まずは落ち着いて調べることも大切です。
(※)屋根材の耐用年数は記事の後半で詳しく解説しています。
② 自治体や公共機関を装い点検を促す
「市から委託を受けて点検しています」「自然災害による調査を区で行っています」など、自治体や公共機関を装い、屋根の点検訪問を行うケースも見受けられます。
こうした訪問をきっかけに屋根に人を上げてしまい、いつの間にか大切な屋根材が破損しているケースも後を絶ちません。特に台風や自然災害の後に急増するため注意が必要です。
③ 無料点検を装い元々なかった傷をつけられる
「弊社の点検は無料です、ぜひ点検させてください」と突然訪問してくる業者は要注意です。無料なら安心だと思って屋根に上らせてしまうと、実際には何の異常もなかった屋根に傷をつけられる悪質なケースもあります。
わざと破損・汚損させたにもかかわらず、「こんなにダメージがありましたよ」と写真や動画を撮影し、家主側に見せるのです。
家主側はダメージを見せられると信じてしまいやすく、「すぐに修理しないと雨漏りする」「放置すると家全体が傷む」と不安をあおられ高額のリフォーム契約を結んでしまう傾向があります。
突然の無料点検は安易に応じるのではなく、必ず名刺や会社情報を確認し、信頼できる業者かどうかを調べてから依頼することが大切です。
④ 即日契約を迫る
「今日なら安くできる」「今すぐ契約しないと危険」と強引に契約を迫る行為も典型的な屋根リフォーム詐欺の手口です。冷静に考える時間を与えないように、玄関に居座るなどの行為も見られます。
こうした行為は恐怖心を与える行為であり、困ったら速やかに警察へ通報することが大切です。
⑤ 高額の費用を請求する
契約前の見積もりが不透明なまま高額を請求される、または契約後に追加費用を次々と上乗せされる被害も多く報告されています。
最初は相場よりも安い見積もりを出していたにもかかわらず、工事が終了した後に高額の費用を請求する行為も多発しています。
高額請求の被害を未然に防ぐためには、複数の会社の見積もりを取得しじっくりと費用や対応を比較した上で、契約することが大切です。
このとき、不当な中間マージンを上乗せしていない「工事店」を選ぶように注意しましょう。
典型的な詐欺トーク集
では、実際に典型的な詐欺の話術にはどのようなものがあるのでしょうか。よくある詐欺トークを紹介します。
- 「屋根が壊れています。このままでは雨漏りしますから点検させてください」
- 「今日契約すれば半額にできますよ、他社より圧倒的に安いです」
- 「市から委託されて来ました、安心して無料点検を受けてください」
- 「ご近所で工事をしていたら、お宅の屋根が傷んでいる様子が目に留まりました。1度弊社で点検しませんか」
このようなトークを巧みに用いて、屋根リフォームの詐欺たちが近付いてきます。トーク集をしっかり覚えておき、詐欺が発生しないように注意しましょう。
「屋根が壊れています」と言われたら?
ご自宅の屋根について、屋根リフォームの業者を名乗るから「お宅の屋根は壊れていますよ」と言われたら、一体どうすればよいでしょうか。
誰でも専門家を名乗る人から、屋根のダメージを指摘されたら不安を感じるものです。しかし、まずは慌てずに以下3つの対応を行いましょう。
・1つの会社の言葉を鵜呑みにせず、相見積もりを取る
・別の家族や親戚にも相談してから契約を決める
・あやしい会社ではないか、インターネットで検索する
このように、すぐに契約をするのではなく相談や検索を行うことで、ご自身が詐欺に巻き込まれるリスクは大きく減らせます。
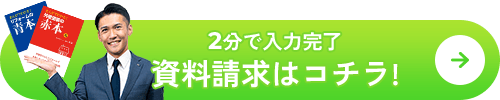
屋根リフォームの詐欺を見極める3つのヒントとは

屋根リフォームの詐欺が横行していたとしても、実際にご自宅の屋根が傷ついていたり、時間の経過とともに傷んでしまったら、リフォームを行う必要があります。
では、屋根リフォームを実際に依頼する際には、どのように詐欺を見極められるでしょうか。本章では詐欺を見極める3つのヒントを解説します。
① 強引に迫られてもすぐには契約しない
訪問業者の中には「今日契約すれば半額になる」「今すぐ修理しないと大変なことになる」と不安をあおり、その場で契約を迫るケースが後を絶ちません。
しかし、そのような急かし方は典型的な詐欺の手口です。冷静に判断するためにもその場で契約せず、家族や信頼できる友人や知人などへ相談しましょう。
高額な工事では、即決してしまうと後から取り返しがつかないトラブルにつながります。
② 口コミや会社情報を調べる
契約を検討する際には、インターネットでの口コミや評判を確認することに加え、会社の所在地や代表者情報など、会社の存在についても調べることがおすすめです。
詐欺の場合は実在しない住所の名刺を持参したり、事務所の実態がない「ペーパーカンパニー」である場合もあります。
会社名のみ頻繁に変えて、過去の悪評から逃れている会社も存在するため住所や電話番号も検索することが大切です。
③ 必ず契約書を取得する
口約束や見積書だけで工事を進めることは、後に大きなトラブルに発展するおそれがあります。工期や金額、保証内容を明記した契約書を交わすことが大切です。
詐欺会社の中には、契約書の取り交わしをあいまいにするケースもあります。こうした態度が見受けられたら、契約を控えるようにしましょう。
もし詐欺に遭った・遭いそうになったら?相談先とクーリングオフ制度

注意していても、屋根リフォームの詐欺に遭ってしまう可能性はゼロではありません。では、詐欺に遭ってしまったときはどのように対処するとよいでしょうか。
本章では詐欺にあったときの相談先や、クーリングオフについてわかりやすく解説します。
クーリング・オフ制度を活用する
訪問販売でのリフォーム契約は、強引な手法の契約が多く消費者保護の観点からクーリング・オフ制度が適用される可能性があります。
クーリング・オフとは一定の期間内であれば無条件で契約を解除できるもので、法律上、契約書を受け取ってから 8日以内 であれば、理由を問わず解除可能です。
しかし、適用要件が設けられており、実際の利用には注意点もあります。
- 書面やメールなど(電磁的記録)で通知する
電話や口頭での解約申し出は法的効力が弱いため、内容証明郵便など証拠が残る方法で「クーリングオフ通知」を送付することが推奨されます。 - 8日間の起算点に注意
クーリング・オフができる期間は限られており、日数のカウントには注意が必要です。カウントは「申込書面もしくは契約書面を受け取った日」から始まります。契約日そのものではなく、業者が交付すべき書面(法律で定められた要件を満たすもの)を受け取った時点が基準です。 - クーリングオフできないケースもある
自ら業者を呼び寄せて契約した場合など、契約方法によってはクーリング・オフが適用されないことがあります。判断に迷う場合は弁護士や国民生活センターに早急に相談することが重要です。
参考:独立行政法人 国民生活センター クーリング・オフ
消費生活センター(国民生活センター)
「怪しい」と思ったら、まずは消費者センター(国民生活センター)に相談することがおすすめです。
消費者ホットライン(188)に電話をかけると自動的に地域の消費生活センターにつながり、専門の相談員が対応してくれます。
訪問販売やリフォーム契約に不安を感じた場合、契約前であっても相談することが可能です。また、すでに契約してしまった場合でも、クーリング・オフ制度の適用可否や返金交渉の方法など、具体的な助言を受けられます。
「もしかしたら自分だけが心配しすぎているのかも…」と思う必要はなく、少しでも不安を感じたら早めに188へ相談することが、被害の拡大を防ぐ第一歩になります。消費者ホットラインなどについては、以下リンクをご確認ください。
参考:独立行政法人 国民生活センター 全国の消費生活センター等
弁護士
屋根リフォームの詐欺が疑われる場合、弁護士に相談することで返金請求や訴訟対応を依頼することも可能です。
弁護士は法律の専門家として、契約内容の適法性をチェックし、クーリング・オフや消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法など、消費者を守る法律を駆使して交渉を行います。
弁護士が代理人として対応すると、依頼者側には電話やメールなども入らなくなるため、心理的な負担を大きく減らせることも大きなメリットです。
費用が心配な方には、各地の弁護士会や法テラス(日本司法支援センター)で無料相談や費用の立替制度を利用できる可能性もあります。トラブルが長引く前に早めに専門家に相談することが、被害回復の近道です。
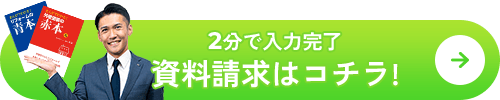
詐欺に遭わないための日頃の対策方法はある?

日頃から詐欺に備えて、やっておくべき対策はあるでしょうか。この章では誰でも簡単にできる、詐欺に遭わないための対策方法を3つにわけて解説します。
定期的にメンテナンスを受けよう
信頼できる業者に定期点検を依頼しておくと、突然の訪問営業に惑わされにくくなります。
定期的に屋根の状態を把握しておけば「屋根が傷んでいますよ」と言われても冷静に判断でき、不要な契約を防ぐことにつながります。
訪問営業は一切受けない
「訪問営業とは一切契約しない」と家族でルールを決めておくのもおすすめです。特に高齢のご家族が一人で対応することが多い場合は、あらかじめ「訪問営業には応じない」と徹底しておくことが望ましいでしょう。
インターホン越しに「必要ありません」と伝えるだけで十分で、引きさがってくれることが多いため、迷わず断ることも大切です。
断りにくい場合は「親戚が工務店をやっていて、その人に任せているから」などと伝えることがおすすめです。
日頃から家族間で情報を共有する
屋根リフォームの詐欺など、住まいに関する詐欺は高齢者や単身世帯が狙われやすく、誰にも相談できない環境の方がターゲットになる傾向があります。
離れて暮らす家族がいる場合、詐欺への注意喚起や住まいの状態を相談しあうなど、日頃から家族同士が連絡を取り合い、詐欺に備えておくことが大切です。
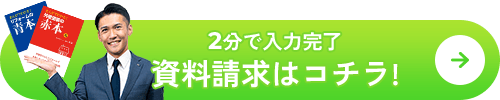
屋根のリフォームはいつするべき?

屋根のリフォームを検討する場合、詐欺にあわないためにも適切なリフォームのタイミングを知っておくこともおすすめです。
そこで、この章では事前に押さえておきたい屋根リフォームのタイミングを紹介します。
屋根の種類別|適切なリフォームタイミング
屋根の寿命は種類によって異なりますが、一般的な戸建住宅の場合、新築後10年を目安にメンテナンスが行われています。このタイミングで屋根をチェックされるケースも多いでしょう。
また、屋根材にはそれぞれ耐用年数があるため、適切なリフォームのタイミングは寿命を迎える前に行うことが大切です。
| 屋根材の種類 | 耐用年数の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 釉薬瓦(ゆうやくがわら) | 60年 | 粘土でできた瓦を釉薬でコーティングしたもの。最も長寿命で、日本の伝統的な屋根材。陶器瓦(とうきがわら)と呼ばれることもあります。 |
| 銅板 | 50~60年 | 軽くて丈夫な金属屋根。経年変化で色が変わっていくのが特徴です。 |
| ガルバリウム鋼板 | 40年 | 軽量で耐久性・耐震性に優れる金属屋根の一種。近年、多くの住宅で使われています。 |
| スレート系 | 30~50年 | セメント成分に繊維質の材料を織り交ぜてできた薄い屋根材。日本の多くの住宅で使用されていますが、定期的なメンテナンスが重要です。 |
| セメント系 | 30~40年 | セメントと砂を原料を主成分とする瓦状の屋根材。定期的な塗装が必要になります。 |
自然災害で被害に遭ったときの対処法
台風や突風などの自然災害の後は、屋根に甚大な被害が発生していることが少なくありません。
まずは、信頼できるリフォーム会社に被害状況の確認と応急処置、修理のお見積りを依頼しましょう。
また、加入されている火災保険で修理費用をまかなえることも多いので、損害保険会社に火災保険の適用範囲を確認しましょう。
公的な支援や税金の減免措置を受ける際には、自治体に罹災証明書(被害の程度を公的に証明する書類)を申請します。
被害が大きい地域では、修理を行うリフォーム会社も多忙となり対応に時間がかかります。
そうした地域では、「早く直してほしい」という不安につけ込む悪質な詐欺業者が増える傾向があります。
そういった業者は、相場より高い費用を請求してくるケースもあるため、十分に注意しましょう。
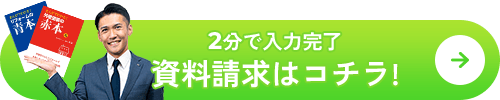
よくある質問(FAQ)

この章では、屋根リフォームでよくある質問を紹介します。
Q1. しつこい屋根修理営業の断り方を教えてください
「必要ありません」「家族と相談します」「親戚が工務店をやっていてその人に任せている」と毅然と断りましょう。ドアを開けずに対応することも有効です。
無理に部屋を開けようとした場合は、警察に通報することも検討しましょう。
Q2. 屋根の詐欺は警察に相談できますか?
契約や詐欺に関する警察への相談も可能です。
ただし、被害金の回収などを依頼したい場合、民事分野のご相談に該当するため警察では対応できません。消費者センター(国民生活センター)や弁護士へ相談しましょう。
Q3. リフォーム詐欺のターゲットになりやすい人はいますか?
屋根以外でも、リフォームにおける詐欺では相談できる人が少ない高齢者世帯や一人暮らし、災害直後で不安な状態の世帯が狙われやすい傾向があります。
不安に付け込む手法が詐欺の大きな特徴です。この特徴を押さえた上で、日頃から詐欺に遭わないように対策を講じておきましょう。
まとめ

屋根リフォームを巡る詐欺被害は全国で増加しており、国民生活センターや警察庁によると「点検商法」など悪質な手口が多発しています。
特に高齢者世帯が狙われやすい傾向があるため注意が必要です。
「今すぐ修理が必要」「今日なら安くなる」と契約を迫るケースや、無料点検を装い破損を作り出す話術に十分ご注意ください。
被害防止には訪問営業に応じない・複数業者から相見積もりを取る・契約書を必ず交わすことが重要です。
万一の場合は国民生活センター(188)や弁護士へ早急に相談しましょう





